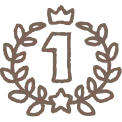未婚化・晩婚化や少子化が注目を集める時代ですが、夫婦や婚活中の人を対象としたアンケートを見ると、多数が「将来は子どもが欲しい」と回答しています。多くのカップルにとって、「子どもを持つこと」は大切な将来の夢の一つだと言えそうです。しかし、望んで子どもを生んだにもかかわらず、子育て期の夫婦の結婚満足度は決して高くありません。それどころか、妻の満足度は子どもの成長に比例するかのように、低下してしまうのです。この記事では、家族心理学の研究をもとにその原因を解説していきます。子育て中のご夫婦や、将来子どもを望んでいるカップルは、不仲になる原因を知り、早めの対策を取ってください!
目次
少子化時代の夫婦は子どもを望んでいるのか?
近年、日本では未婚化・晩婚化や少子化が注目を集めています。実際に、日本では未婚者の割合が増加しており、子どもの数も減り続けています。2024年の出生数は72万988人となり、統計を取り始めてから最少となりました。しかも、この数字は日本で暮らす外国人夫婦の子どもも含まれるため、日本人に限定すると70万人を切ると予想されているのです。
「では、最近の夫婦は子どもを望んでいないのでしょうか?」
例えば、本記事執筆中の2025年3月には、15歳〜39歳の男女の52%が「子どもはおらず、子どもは育てたくない」と回答したという調査結果が大きな話題を呼んでます。これは、子育て政策などの専門家である末冨芳教授(日本大学)の研究グループが行った調査の結果です。
この数字だけを見れば、「最近の夫婦は子どもを望んでいない」という結論になりそうですが、少し冷静に結果を見てみると、より複雑な問題が見えてきます。特に重要な点は、収入と「子どもがいること/望むこと」の間に相関関係があるということです。未婚化や少子化が進んでいる現代であっても、大企業勤めの人や公務員に限ってみれば、1980年〜90年代と比較しても、結婚している人、子どもがいる人の割合はほぼ変わっていないのです。
つまり、現代の若い世代は「子どもを望んでいない」というよりも、「経済的に厳しくて子どもを持つ未来を想像できない」という可能性が高いのです。
実際に、婚活中の男女を対象とした別の調査では「20〜30代の若い世代では9割近くが希望している」という結果も報告されています。調査対象や方法によって、結果に幅はあるものの、若い世代の夫婦や婚活者を対象とした場合は、どの調査でも概ね8割前後が「将来は子どもが欲しい」という回答をしているようです。
つまり、既婚者や結婚に向けて動き出している人たちの多くは「子どもが欲しい」と考えていることがわかります。
また、若い世代の結婚に関する研究をみていくと、「収入」と「結婚の意思」にも相関関係があることがわかります。このことから、そもそも結婚していたり、婚活をしたりしている人たちは、「子どもがほしい」と思えるだけの経済的余裕がある人の割合が高いと考えられます。
若者の結婚観については、こちらの記事も参照してください。
望んでいた子どもが生まれたのに、結婚満足度が下がるのはなぜか?
これまで見てきた通り、少子化の時代であっても、夫婦や婚活中の人の多くは子どもを望んでいるようです。
また、統計データによれば、既婚男性の年収は未婚男性よりも高い傾向にあります。例えば、2022年時点のデータでは、男性の平均初婚年齢にあたる30〜34歳の未婚男性の収入が約377万円であるのに対して、既婚男性の平均年収は約506万円でした。
つまり、同世代と比べると既婚男性や婚活中の男性は、経済的に安定している傾向があります(※)。
※ただし、独身であることや子どもがいないことと、男性の収入が必ずしも関係するわけではありません。これまでは「当たり前」と見なされてきた結婚や出産・育児も「たくさんある選択肢の1つ」という認識が広まっており、収入の多寡にかかわらず、独身や子どもを産まない生き方をあえて選択する人も増えています。
結婚して子どもがいる夫婦の多くは、子どもを望んでおり、経済的にも安定している場合が多いのです。言い換えれば、「自分たちが望んでいた子宝にも恵まれ、同世代と比較すると経済的にも安定しているカップル」だということです。
一見すると、子どもの誕生により、夫婦としての幸せも最高潮に達してもおかしくないように思えます。
それにもかかわらず、なぜ多くの夫婦の結婚満足度は子どもの成長にともなって低下してしまうのでしょうか?また、なぜ妻側の満足度の方が顕著に低いのでしょうか?
今回の記事で主に参考にしている論文では、子どものいる夫婦に着目して、ライフステージによる結婚満足度の変化を分析しています。今回は、この調査をもとにこれらの原因を探っていきましょう。
①夫の仕事が忙しくなる時期と子育てで悩む時期が重なる不幸
この論文では、調査結果をもとに、子どものいる夫婦を子ども(第一子)の年齢に応じて、「未就園児」、「保育園/幼稚園」、「小学生」、「中学・高校生」、「大学生」の5つのグループに分けて分析を行いました。
この調査によると、第一子が「小学生」の時期に夫婦の結婚満足度は一気に下がります。また、その直前にあたる「保育園/幼稚園」の時期では、夫の満足度は上昇している一方で、妻の満足度は微減していくため、夫と妻の間でかなりの結婚満足度の差が観察されました。
この背景には、ちょうどこの時期に夫婦のすれ違いを招く「不幸な社会の仕組み」が隠れています。
女性の社会進出が進んできたとはいえ、いまだに「主な稼ぎ手は男性」という考えは根強く残っています。子どもの進学などを考えると、実際にお金が必要なことも事実です。
子どもの誕生をきっかけに、父親(夫)が「家族のために仕事を頑張らなければ!」と必死になって仕事をすることも多いでしょう。その努力が実って、職場で認められ、役職が上がり、責任のある仕事を任されるようになるのが、30代半ば〜40代半ばの時期です。
2023年の厚生労働省の調査によれば、「係長級」の平均年齢は45.4歳。業界や企業規模によって役割は異なるとはいえ、責任のある立場です。責任が重くなると同時に、労働時間も長くなっており、30代、40代、50代と年齢が上がるにつれて仕事はどんどん忙しくなっていきます。
男性の平均初婚年齢(31.1歳)を踏まえると、第一子が「保育園/幼稚園」や「小学校」という時期は、この「仕事で責任が増え、労働時間が長期化する30代半ば~40代半ば」とピッタリと重なります。
一方で、子どもが家庭外の集団に参加し始める「保育園/幼稚園」入園や、習い事や塾などさらに活動範囲が広がる「小学校」の時期は子育てに関する悩みも増えますし、様々な選択を迫られる時期です。子どもと接する時間の長い母親(妻)は、第一子の成長にともなう急激な環境の変化の真っただ中にいます。
つまり、夫の「家族のためにも頑張ってきた仕事が最も忙しくなる時期」と、妻の「子どもの成長に伴って、悩みや選択が増える時期」が重なってしまっているのです。そのため、どうしてもすれ違いが生まれやすくなってしまう仕組みになっているのです。
②相手の「性役割観」の違いをお互いに認識できていない問題
この論文の特徴は「性役割観」に複数の角度から焦点を当てて、分析している点にあります。子どもを持つ夫婦270組を対象とした調査の結果、明らかになったのは、ライフステージが進むにつれて、「性役割観について『“私と夫は違うだろう”と考えている妻』と『“僕と妻はほぼ同じだろう”と考えている夫』という夫婦間の齟齬が生じてきているということです。詳しく解説していきます。
性役割観ってなに?
性役割観とは「性別に基づいて、どのように役割や行動を期待するか(されるか)」という認識のことです。中でも最も典型的なものの一つが、「男は仕事、女は家庭」という夫婦間での役割に関する意識です。
この性役割観は、社会的に共有されている部分が多いものの、育ってきた環境や周囲の状況によって異なるものです。例えば、共働きの家庭で育った人と、母親が専業主婦の家庭で育った人とでは、子どもを持つ女性の性役割観が異なるのは、当然のことでしょう。
パートナーにどのような役割を期待するかは個人の自由ですが、夫婦間でお互いの性役割観がずれており、そのずれに気が付いていないと悲劇は起こります。
「子育ては母親中心で行うべきもの」という価値観の夫は、子育ての大部分を妻が担うことを期待しています。これに対して、妻の側が「父親も同じだけ子育てに関わるべきだ」という性役割観であった場合は、「子育ての負担が自分にばかり押し付けられている」と感じてしまうでしょう。
この性役割観のずれが、結婚満足度を大きく下げる原因なのです。
年々広がる「相手の性役割観」の推測と実態のずれ
この論文の非常に面白い発見は、「性役割観のずれが、結婚満足度を低下させる」という事実の中身をさらに深堀りしている点です。分析の結果、満足度の低下に大きな影響を与えるのは「実際の性役割観のずれ」ではなく、「自分の性役割観と、相手が自分の性役割観をこう思っているだろうという予想(推測)のずれ」だということがわかりました。一見ややこしいですが、重要なポイントなので整理していきましょう。
まず、これまでの研究で「性役割観差」や「結婚満足度」の差異を調査する場合、注目されてきたのは主に2つの差異でした。
(1)妻の自己評価と夫の自己評価の差(=夫婦の間のずれ)
この場合は、数字が大きくなればなるほど「夫婦間で性役割観の差が大きい」、「結婚満足度の差が大きい」ということになります。例えば、「男は仕事、女は家庭」という価値観の夫と、「家事は半分ずつ分担すべきだ」という考えの妻の間ではこの数字が大きくなります。
(2)理想と現実との差(=理想と現実のずれ)
この場合は、妻(夫)が理想とする相手の行動と、実際の相手の行動に対する評価の差を計算します。数字が大きいほど、「理想と現実の結婚生活のギャップが大きい」ことを意味します。例えば、「料理は交代で作る」という理想がある場合、現実に料理をする割合が不平等であれば、理想と現実のずれを表す数値が高くなります。
今回の調査ではこの2つに加えて、もう一つの「差異」に注目しています。
(3)自分の性役割観の自己評価と、パートナーの性役割観を推測した評価(自分が思う自分の性役割観ー自分が思う相手の性役割観=自分にとっての「現実」的な差)
この場合は、妻(夫)が目線からみた「自分と妻(夫)の性役割観の差」が大きければ多いほど、数字が高くなります。例えば、「自分は家事は半分ずつやるべきだと考えているが、夫は『家事は女の仕事』と思っているに違いない」と妻が推測している場合は、この数字が大きくなるのです。この時、実際に夫が「家事は女の仕事」と思っているかは関係ありません。
この(3)の分析でわかるのは、妻(夫)からみた「主観的な夫婦の価値観の差」なのです。
性役割観のずれが「大きくなってる」と思う妻、「少なくなっている」と思う夫
価値観、特に夫婦生活では重要な性役割観が近いに越したことはないものの、(1)の性役割観の差(妻の自己評価と夫の自己評価の差)が大きいからと言って、直ちにトラブルになるわけではありません。相手とのずれを互いに認識できていれば、お互いに歩み寄ることは十分に可能です。
より深刻なのは、夫と妻の間で(3)性役割観の推測値の差(自分が思う自分の性役割観ー自分が思う相手の性役割観の差)に開きがあり、その差を互いに認識していない場合です。
この調査によると、「未就園児」の子どもを持つ夫婦の間では「性役割観の推測値」にはほとんどずれがありませんでした。夫も妻も「自分と相手の性役割観はこのくらい違うだろう」という価値観の差を、同じように捉えていたのです。
しかし、この差は広がっていきます。特に「保育園・幼稚園」「小学生」と子どもが成長する中で、「夫側の推測値の差」が低下する一方で、「妻側の推測値の差」は上昇します。
言い換えれば、子どもが成長するにしたがって、夫は「僕と妻の考えはほとんど同じだろう(差は少なくなっている)」と考えるようになり、妻は「私と夫は違うだろう(差は広がっている)」と考えているようになっていくのです。
夫の基準:「自分の父親と比べて、自分はどうか」
夫婦のすれ違いの典型的な理由である「家事の分担」については、例えば「男性は無意識に自分の父親と比べて自分を評価している」と言われています。
現在30~40代の男性の父親といえば、まさに昭和真っ只中の時代に生まれ育った世代です。「男は仕事、女は家庭」という価値観が当たり前だった世代です。
近年では、「家事は夫婦で分担するのが当たり前」という認識が広まってきており、実際に男性の家事時間は少しずつではあるものの、年を追うごとに増加し続けています。
つまり、「自分の父親との比較」で考えている男性からすれば、「自分は家事も頑張っている」という自己評価になるのは自然なことなのです。
妻の基準:「実際にどれだけの割合で分担しているか」
一方で、毎日家事をしている妻は「相手の父親と比べて、自分の夫が頑張っているか」という基準では評価しません。「自分自身の負担に対して、夫はどのくらい負担しているか」という「実際の家事分担(自分との比較)」が基準になるのは自然なことでしょう。
女性の社会進出が進んでいるということは、要するに「女性の労働時間が長くなっている」ということでもあります。つまり、家事以外の仕事もどんどん忙しくなってきています。
そんな中、男性の家事時間はいまだに女性と比べると顕著に低いままです。つまり、共働きの女性から見れば、自分だけが「仕事+家事」の負担を抱えている状態なのです。
この根本的な部分でのすれ違いが、日々のストレスとなって(妻側に)蓄積してしまい、結婚満足度を低下させてしまうのです。
「相手の考えを推し量る」のはやめにしよう!
さて、ここまでお読みになっていただいた読者のなかには、「どうすればいいんだ」と頭を抱えている方もいるかもしれません。確かに、この問題は深刻であり、明快な解決策はありません。
すれ違いが起きる原因はいくつも考えられるものの、共通して言えることは「自分の価値観を相手もわかっているはずだ」、「愛情があれば気持ちが伝わるはずだ」という思い込みにあります。
しかし、多くの研究が明らかにしてきた通り、夫婦であっても「価値観は違って当たり前」であり、むしろ別の基準でものごとを評価してしまうものなのです。
問題は、お互いの基準のずれをお互いに認識していないことにあります。
先ほどの例に戻れば、夫側は無意識に「自分の父親よりも家事をやっているから十分だろう」と思い込み、妻に「どのくらいの家事分担が理想?」と問いかけていないのです。
一方で、妻側は「私ばっかり家事の負担が多い」という不満を抱えているにもかかわらず、「どうせこの人(夫)は『家事は女の仕事』と思っているんだろう」と決めつけて対話を諦めてしまっていたりするのです。
今回ご紹介した研究をはじめ、家族心理学の研究が明らかにしてきたことの一つは、実は「実際の価値観の違い」ではなく、この「相手と自分は同じだ」あるいは「相手と自分は違う」という思い込みがすれ違いの原因であるということです。
まずは自分の素直な気持ちを開示するところから始めることができれば、例え「すれ違い」が生じてしまっても、早期に話し合って妥協点を見つけることができる可能性が高いでしょう。すれ違いを放置した結果、最悪の結末を迎える前に、ゆっくり会話する時間を持ってください。