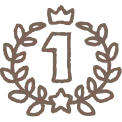近年、熟年離婚の割合は増加の一途をたどっています。2022年には、熟年離婚の割合が約23.5%に上り、統計が開始された1947年以降で過去最高となりました。その背景には、夫婦の結婚満足度の差があります。夫婦の結婚満足度は時間とともに低下する傾向にあり、なかでも夫が妻の満足度の低下に気が付かず、すれ違いによる不満が蓄積した結果、熟年離婚につながっている可能性が家族心理学の研究で指摘されています。この記事では、その実態をデータをもとに分析したうえで、その解決法を具体的に提示します。
目次
熟年離婚の大きな原因は「妻と夫の認識の差」
- 「夫に比べて、妻の結婚満足度は顕著に低い」
- 「満足度の差は結婚後の年数を経るごとに大きくなっていく」
- 「妻側に満足度の低下がみられるにもかかわらず、それを夫は認識していない」
これまで家族心理学の研究が明らかにしてきたのは、妻を持つ男性からすれば背筋が凍りつくような日本の夫婦の実態です。こうした妻と夫の認識のズレや満足度の差が蓄積した結果が、近年増加している「熟年離婚」に繋がっていると考えられます。
もちろん、お互いに相手との生活に嫌気がさしてしまっているのであれば、離婚も選択肢の一つでしょう。「夫婦の三分の一が離婚する」と言われる現代社会では、離婚に対する偏見はかなり少なくなっています。無理してまで結婚生活を続ける必要はありません。
しかし、現実には「結婚生活に概ね満足していた夫が、ある日突然、妻から離婚を突き付けられる」というパターンが少なくないのです。「離婚を切り出す」という決断をするまで不満が蓄積してしまった後になって、いまさら慌てたところで時すでに遅し。関係の修復は望むべくもないでしょう。
今回は、熟年離婚の状況について統計データをもとに整理したうえで、家族心理学の研究をもとに、熟年離婚の原因である「結婚満足度のジェンダー差」について解説していきます。
統計データで見る熟年離婚の実態
先に述べた通り、熟年離婚の割合は増加傾向にあり、2022年には統計開始後で最高となる23.5%を記録しました。つまり、離婚した夫婦の4組に1組は熟年離婚だということです。
熟年離婚とは、一般的に「結婚から20年以上経過した夫婦が離婚すること」を指します。
離婚する夫婦全体でみると、同居開始2〜3年目の夫婦の割合が最も高く、年数が経過するごとに割合が下がります。婚約や結婚を機に一緒に生活を始めた後に、離婚の主な要因である「価値観のずれ」が表面化してしまい、離婚に至るパターンが多いようです。
どれだけ長い交際期間を経て結婚しようとも、家族として一緒に暮らしてみて初めて知る相手の一面は必ずあります。なかには、結婚後に決定的な価値観の相違が明らかになってしまい、今後の将来を描けなくなるカップルがいるのは仕方がないことでしょう。
つまりは、「相性が悪いことが結婚後に発覚した」ということであり、やや極端な言い方をすれば「間違った相手と結婚してしまった」ことが離婚の原因だと言えます。
離婚した夫婦の約3割を占める「5年未満の夫婦」の多くは、このパターンに該当すると考えられます。この場合、「無理に結婚生活を続けるよりも、早めに離婚した方がお互いにとって幸せ」ということも少なくありません。
しかし、熟年離婚の場合は、20年以上に亘って一緒に生活をしてきたカップルの話です。場合によっては、自分の親よりも長い時間を同じ屋根の下で過ごしてきた特別な関係であり、離婚理由も結婚初期の離婚とは異なると考えられます。
熟年離婚の原因は、「相性が悪かった」のではなく、「もともとは良かった相性が徐々に悪くなってしまった」ことが原因なのです。「根本的な部分で価値観が合わなかった」のではなく、「小さな価値観のずれの積み重ねが、ついには離婚にまで発展してしまった」ということもできるでしょう。
熟年離婚の件数は、この小さな価値観のずれを放置したまま、徐々に関係を悪化させてしまった夫婦の数をそのまま反映していると考えられます。
家族心理学の研究が明らかにするのは、夫婦間のすれ違いの背景にあるのは、「相手は○○だろう」という思い込みが持つ影響の大きさです。「小さな認識のズレ」や「口に出すほどでもない不満」の蓄積が、幸せだったはずの夫婦が別々の道を選ぶことに繋がってしまうのです。
「自分の妻は大丈夫だろうか?」と不安になった男性だけでなく、「すぐに離婚を切り出すほどではない小さな不満」を抱えている女性もぜひご一読ください。
熟年離婚につながる「結婚満足度のジェンダー差」
夫婦生活が長くなるにつれて、子育て、転職、親の介護などなど様々なライフステージの変化に直面します。そのため、どれだけ仲の良い夫婦であっても「ずっと新婚の時のまま」ということはありえないでしょう。関係性は変化するのが当たり前なのです。
夫婦として苦楽を共にするなかで、相手への愛情が深まっていく…という変化が理想ですが、家族心理学の観点から行われた調査をみると、その結果は衝撃的なものです。
まず、男女問わずに、ライフステージによる夫婦関係の満足度は結婚の年数とともに低下していく傾向があります。特に、中年期以降になると妻の満足度が夫よりも顕著に低くなることが知られています。
この「結婚の満足度のジェンダー差」のなかでも、結婚直後は同じ水準である夫婦の結婚満足度が、夫は6~15年目にかけて上昇する時期がある一方で、妻は一貫して低下していくという調査結果は、多くの男性にとって目を覆いたくなるようなものでしょう。
熟年離婚される夫は妻の結婚満足度の低下に鈍感?
なぜ夫婦の結婚満足度の差は広がってしまうのでしょうか?
もし夫婦喧嘩の回数が明らかに増えていたり、夫婦関係を一気に冷え込ませるような事件が発生したりした場合、どちらの満足度も同じように低くなると考えられます。
それにもかかわらず、夫婦の結婚満足度には偶然では片づけられないレベルのジェンダー差があることが知られてます。
先にも述べた通り、ある調査によると、結婚後6〜15年目の夫婦に至っては、夫の満足度が高まる一方で、妻の満足度は下がり続けるという現象すら報告されているのです。
この夫婦間での深刻なギャップを理解するためには、夫婦の結婚継続の理由を調査した別の調査が役に立ちます。
妻の結婚満足度が高いパターンの夫婦の場合は、妻も夫も「信頼」「尊敬」「思いやり」など、相手といることで得られる安心感や満足感などを結婚継続の理由として回答しました。
一方で、妻の満足度が低いパターンでは、夫の半数以上が「かけがえのない大切な人」などと妻のことを表現しているにもかかわらず、妻は「子どもがいるから」や「経済的な支援者である」ことなどを結婚継続の理由に挙げています。
裏を返せば、妻に「子どもがいなければ離婚している」「お金を持ってくる人」としか思われていないにもかかわらず、多くの夫がその妻の気持ちに気づいていないのです。
「妻のことをかけがえない人と思っている夫」と「経済的な支援者としか見ていない妻」がかなり存在するというデータを前にして、あなたはどう思うでしょうか?
夫の立場に立てば、「愛しているのに、自分をATM扱いするなんてひどい妻だ!」
妻の立場に立てば、「妻の気持ちが全く分からない夫だから、徐々に愛情がなくなってしまったんだ!」
このような争いになるのは目に見えています。この意見は、どちらもある意味で「真実」であり、この論争でどちらが勝ったところで夫婦関係は壊れたままです。こうなってしまっては、もはやほとんど手遅れです。その前に手を打たなければなりません。
熟年離婚の予防法:相手に期待を伝える/相手の期待を知るためのアクションをとる
家族心理学の研究が明らかにしてきたのは、「夫と妻の結婚満足度には差がある」ということだけではありません。例えば、妻と夫の満足度の差は、第一子が「未就学児」の間ではあまり差がないにもかかわらず、「幼稚園・保育園」と「小学生」の時期に顕著に大きくなることも明らかになっています。
詳しくは別の記事で解説しますが、子どもの成長にともなって日常の環境が変わるなかで、夫婦の間ですれ違いが生じていることがわかります。この時期に生じてしまった「結婚満足度のジェンダー差」は、子どもが成長していってもなかなか埋まることはありません。
子どもが「大学生」になる時期には夫婦ともに満足度がやや上昇する傾向がみられるものの、その背景には、満足度が極端に低い夫婦が離婚して統計から抜けたことも影響していると考えられます。
「子どもに関する悩みがひと段落して、夫婦二人で向き合う時間が取れるようになった」というポジティブな理由で満足度が高まる場合もあるものの、「子どもが成長すれば昔みたいに仲良くなれる」という考えはあまりにも楽観的過ぎるでしょう。
月並みですが、すれ違いの蓄積による熟年離婚を防ぐための解決策は「コミュニケーション」です。すれ違いによって、徐々に結婚満足度が低下していく熟年離婚。その原因は、お互いの不満を認識し合って、解決していくためのコミュニケーションが取れなかったことにあります。
子どもの成長と夫婦の結婚満足度の関係性からも明らかなとおり、ライフステージが変化して生活が変われば、パートナーに期待することも変化します。
このタイミングで適切なコミュニケーションを取り、お互いの期待を認識し、理想と現実のギャップを埋めることができれば、「熟年離婚の芽」を早期に摘み取ることができるでしょう。
そのためには、基本的なことですが、「相手に気持ちを伝えること」、「相手の考えを聞くこと」が欠かせません。この基本を怠らずに、相手と向き合うことこそが、最良にして唯一の「熟年離婚の予防法」なのです。
「熟年離婚の芽」を摘み取る:ライフステージの変化=話し合うべきタイミング
一緒に暮らし始める、子どもが生まれる、産育休から復職する…
このような大きな変化が生じるタイミングでは、多くの夫婦が向かい合って、家事の分担や休日の過ごし方など、これからの生活について話し合っているはずです。
ですが、結婚生活が長くなってくると、夫婦の関係性について話し合う機会は少なくなってしまいます。話し合う機会がないことは、二つの意味で大きな問題だと言えます。
一つ目は、「夫婦であろうと言葉にしないと気持ちは伝わらない」ということです。この点は、多くの研究で繰り返し指摘されています。それにもかかわらず、お互いが「言わなくてもわかってくれているだろう」という思い込みに陥ってしまうことも、家族心理学の分野ではよく知られています。
二つ目は、そもそも「自分のなかの、相手に対する期待の変化」を自覚する機会がない、ということです。「相手への期待」は、ある日を境にいきなり180度ガラリと変わるのではなく、日常生活の中で徐々に変化していくものです。その変化は緩やかであるため、自分自身でも気が付かない場合が少なくありません。
話し合う機会がないことで、「相手に対する自分の期待が変化している」ことに無自覚なまま、相手が期待に応えてくれないことに不満を募らせてしまうことになるのです。
これが離婚へとつながる大きな落とし穴です。
家族心理学の研究が明らかにした通り、ライフステージの変化に伴って、夫婦関係は変化するものです。そして、相手の気持ちは、長年共に暮らしている夫婦であっても、言葉にしない限り正確に理解することは不可能です。
「夫婦関係は変化するもの」「パートナーへの期待は変わるもの」という前提に立てば、やるべきことは明白です。
すなわち、定期的に夫婦関係や相手への期待について話し合う機会を設けることです。少なくとも、子どもの進学、職場の部署異動や転職、引っ越しなど、これまでと生活が変わる場合は必ず話し合いの機会を持つべきでしょう。
こうした機会を通じて、お互いが素直な気持ちを開示することができれば、例え「すれ違い」が生じてしまっても、早期に話し合って妥協点を見つけることができる可能性が高いでしょう。すれ違いを放置した結果、最悪の結末を迎える前に、ゆっくり会話する時間を持ってください。