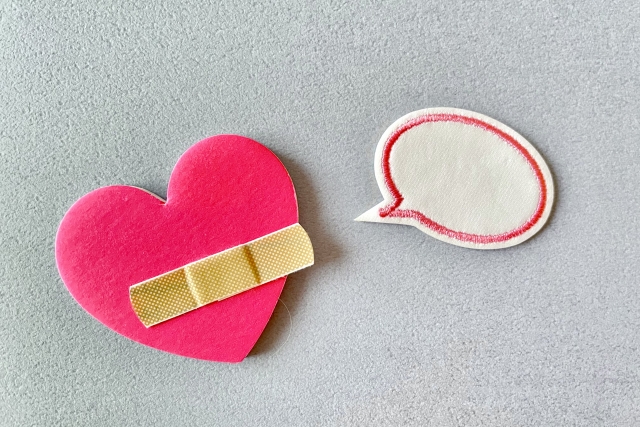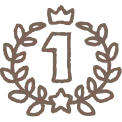ハラスメント加害は、職場や学校、家庭などあらゆる環境で発生する社会問題です。被害者が受ける精神的・身体的な影響は深刻であり、加害者の行動を正すことが求められています。しかし、ハラスメント加害者の更生は簡単なものではなく、個人の意識だけでなく社会全体の理解とサポートが不可欠です。
本記事では、ハラスメントの定義や基準を明確にし、加害者の更生を実現するための視点について解説します。
目次
そもそもハラスメントとは?その定義と基準
ハラスメントとは、「人を嫌がらせること」「いやがらせ」を指します。特に職場におけるハラスメントは大きな関心を集めており、民間会社が行った「2024年ハラスメントに関するアンケート調査」によると、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントの認知度は95%を超えています。ハラスメントをなくすためには、加害者・被害者の双方が正しい知識を持ち、対策を講じることが不可欠です。
現代社会で問題視されているハラスメントにはさまざまなものがあり、職場で発生するハラスメントの定義については以下の記事で詳しく解説しています。
「ハラスメント加害者の意図<被害者が受けた被害」が重視される傾向に
ハラスメント問題において近年重視されているのは、加害者の「意図」よりも被害者が「どのような被害を受けたのか」という点です。これは、ハラスメントの本質が「受け手の感じ方」にあるという考え方に基づいています。たとえば、加害者が「冗談のつもりだった」と言っても、被害者が精神的苦痛を感じた場合、それはハラスメントとして認定される可能性が高くなります。
このような流れは、被害者の権利を守る上で重要な視点であり、社会全体のハラスメントに対する理解を深めるきっかけにもなります。加害者が「つもりではなかった」と主張することは、もはや言い訳にはならない時代になっています。
ハラスメント加害行為はなぜ起こる?主な5つの原因
ハラスメントが発生する背景には、さまざまな要因が絡み合っています。単に加害者の性格や個人的な問題だけでなく、社会全体の構造や価値観が影響を与えていることも少なくありません。
特に、ハラスメントが長年にわたって見過ごされてきた背景には、法制度の不備や認識の甘さが関係しています。加害者が無自覚にハラスメントを行うケースも多く、問題の本質を見極めることが求められます。
ここでは、ハラスメントが発生する主な5つの原因について詳しく解説し、なぜ社会全体での対策が必要なのかを考えていきます。
原因➀:ハラスメントの明確な定義の欠如【認知的不正義】
ハラスメントが発生しやすい理由のひとつに、その定義があいまいであることが挙げられます。法律や社内規定にハラスメントの基準が設けられている場合もありますが、社会全体で統一された基準がありません。そのため、「どこからがハラスメントなのか?」という点が人によって異なり、加害者が自覚を持たないまま行為に及ぶことがあります。
特に、日本社会では「多少の厳しさは必要」「冗談のつもりだった」といった言い訳が通用しやすく、被害者が声を上げづらい状況が生まれやすいです。このような状況は「認知的不正義」とも呼ばれ、問題が可視化されにくい要因となっています。ハラスメントを減らすためには、社会全体で共通認識を持ち、明確な基準を設けることが不可欠です。
原因➁:感情コントロールの能力不足
ハラスメント加害者の多くは、自分の感情を適切にコントロールする力が不足している傾向があります。特に職場といったストレスが多い環境では、怒りや苛立ちを抑えられずに他者に対して攻撃的な言動を取ってしまうケースが見られます。たとえば、上司が部下に対して怒鳴りつけたり、指導という名目で過度なプレッシャーをかけたりすることが挙げられます。
感情をうまく制御できないことで、相手を傷つけてしまい、それが結果的にハラスメントと認定されることもあります。ハラスメント防止の観点からも、加害者側の感情コントロール能力を高めるためのトレーニングが求められています。怒りの感情を適切に処理する方法を学ぶことで、不必要な衝突を防ぎ、より健全な人間関係を築くことができるのです。
原因➂:コミュニケーション能力不足
適切なコミュニケーションが取れないことも、ハラスメントを引き起こす大きな要因となります。相手の気持ちを汲み取ることができず、自分の価値観や考え方を一方的に押し付けることで、無意識のうちに相手を傷つけてしまうことがあります。
特に、指導やアドバイスを行う立場の人が、適切な言葉選びをせずに相手を非難するような表現をすると、それがハラスメントとみなされることもあります。また、非言語的なコミュニケーションの取り方も重要です。表情や態度が攻撃的であったり、相手の話を聞かずに一方的に話し続けたりすることが、ハラスメントの一因となることがあります。適切なコミュニケーションスキルを身につけることは、ハラスメント防止だけでなく、より良い人間関係を築くためにも欠かせません。
原因➃:世代間ギャップ、多様性への理解不足
現代社会において、世代間ギャップや多様性に対する理解不足が、ハラスメントを引き起こす原因となることがあります。特に、価値観が大きく異なる世代が共存する職場などの環境では、昔ながらの考え方が現代の基準に合わず、意図せずハラスメントに該当する行為をしてしまうことがあります。
たとえば、「昔はこれが普通だった」「自分たちの時代には当たり前だった」という発言が、現在の感覚では問題視されるケースもあります。また、ジェンダーや文化の多様性に対する理解が不足していると、無意識のうちに差別的な発言をしてしまい、それがハラスメントと認定されることもあります。時代の変化に合わせて、多様な価値観を尊重する姿勢を持つことが、ハラスメントを防ぐうえで非常に重要です。
原因➄:一部では被害者側の社会的ルール・マナーを欠いた言動が問題視されることも
ハラスメントの議論では、加害者だけでなく、被害者側の行動にも注目が集まることがあります。例えば、職場や学校などの規律を守らず、周囲に対して無礼な態度を取ることが、結果的にハラスメントの原因となるケースもあります。もちろん、どのような理由であれ、ハラスメントが正当化されることはありません。しかし、一部では「注意される側にも問題があるのではないか?」という意見が出ることも事実です。
例えば、仕事のルールを守らない、礼儀を欠くような振る舞いをすることが、上司や同僚との摩擦を生み、それがハラスメントとみなされるようなケースです。このような状況を避けるためには、加害者・被害者の双方が適切な行動を心がけることが重要です。ハラスメントの本質を見極めるためには、一方的な視点ではなく、社会全体のルールやマナーにも目を向けることが必要となります。
ハラスメントが職場に与える深刻な影響
職場におけるハラスメントは、単なる個人間のトラブルではなく、組織全体に悪影響を及ぼす深刻な問題です。被害者が精神的なダメージを受けるだけでなく、職場の雰囲気が悪化し、同僚や上司・部下の関係にも大きな影響を与えます。
さらに、企業の業績や生産性の低下にもつながるため、ハラスメントを防ぐための取り組みが必要不可欠です。ここでは、ハラスメントが職場に及ぼす具体的な影響について、被害者への影響、第三者への影響、そして業績への影響の3つの視点から詳しく解説します。
ハラスメント被害者に対する影響
ハラスメントの被害を受けた人は、精神的・身体的に大きなダメージを受けることが多く、日常生活にも悪影響が及びます。特に、職場でのハラスメントは被害者が逃げ場を失いやすく、継続的なストレスにさらされることで、うつ病や不安障害を発症するケースも少なくありません。
被害者は「自分に非があるのではないか」と自責の念にかられ、仕事のパフォーマンスが低下し、最悪の場合、退職を余儀なくされることもあります。また、職場における人間関係の悪化により、周囲から孤立してしまうことも少なくありません。このような状況が続くと、被害者だけでなく、企業や組織全体にも大きな損失が生じることになります。
第三者に与える影響
ハラスメントは、被害者と加害者だけの問題ではなく、周囲で働く第三者にも深刻な影響を及ぼします。たとえば、同僚がハラスメントを目撃した場合、職場の環境に不信感を抱き、働く意欲を失うことがあります。また、ハラスメントを受けている同僚を見ても「自分が介入しても何も変わらない」「下手に関わると自分も標的になるかもしれない」と感じ、結果的に見て見ぬふりをすることになるケースもあります。
こうした状況が続くと、職場全体の士気が低下し、同僚同士の信頼関係も崩れていきます。さらに、管理職がハラスメントを黙認するような職場では、組織全体に「問題があっても誰も助けてくれない」という風潮が生まれ、職場の健全性が大きく損なわれてしまいます。
職場の業績に与える影響
職場におけるハラスメントは、組織の業績や生産性にも大きな悪影響を及ぼします。被害者がストレスや不安を抱えながら仕事を続けることで、集中力やパフォーマンスが低下し、業務の効率が悪くなることがよくあります。さらに、ハラスメントが横行する職場では、人材の定着率が下がり、優秀な人材が流出するリスクも高まります。企業のブランドイメージにも影響を与え、ハラスメントが原因で企業の評判が悪化すると、採用活動にも支障が出る可能性があります。
また、ハラスメント問題が公にされ、訴訟や行政指導が入ると、企業は多額の賠償金や罰則を受けるリスクを負うことになります。このように、ハラスメントがもたらす影響は、職場の雰囲気の悪化だけでなく、組織の成長や存続にも深刻なダメージを与えるのです。
現代社会におけるハラスメントの問題点
ハラスメントが社会問題として広く認識されるようになった一方で、依然として多くの課題が残されています。被害者が声を上げにくい環境や、加害者の更生が進みにくい法制度など、ハラスメントの根本的な解決を妨げる要因は少なくありません。
特に、日本社会では「被害者にも落ち度があるのではないか」という風潮や、性犯罪をめぐる裁判の判決が加害者に甘いといった問題が指摘されています。ここでは、ハラスメント問題における2つの大きな課題について詳しく解説し、社会全体でどのように改善していくべきかを考えます。
被害者非難に陥りやすい社会全体の取り組み
ハラスメント問題が社会的に認識されるようになったにもかかわらず、被害者が十分に守られていないケースが多く見られます。特に、「被害者にも責任があるのではないか」といった偏見が根強く残っており、被害を訴えること自体が精神的な負担になってしまうことがあります。
例えば、セクシュアルハラスメントの被害者に対して「なぜ抵抗しなかったのか」「なぜその場を離れなかったのか」といった質問が投げかけられることがあります。これらは加害者を免罪するものではなく、被害者の立場を弱める要因となっています。
また、防犯対策の一環として「女性は夜道を避けるべき」「露出の多い服装は控えるべき」といった指導が行われることもあります。しかし、こうした対策は加害者の行動を抑制するのではなく、被害者側に行動の制限を強いるものになってしまいます。その結果、「自衛できなかった被害者が悪い」という誤った認識が広まりやすくなります。
社会全体でハラスメントを防ぐためには、被害者に責任を押し付けるのではなく、加害者が適切に処罰される環境を整えることが重要です。
加害者更生を難しくさせる性犯罪裁判の事例
ハラスメント加害者の更生を困難にしている要因の一つに、性犯罪に関する裁判の判決が加害者に甘い傾向があることが挙げられます。特に、被害者の供述が軽視されたり、加害者の意図や状況が考慮されすぎることで、適切な処罰が下されないケースが見られます。
例えば、フラワーデモの契機になった2019年に発生した事件では、父親による未成年の実の娘に対する性暴力が問題となりました。一審で「被害者が完全に抵抗できない状態だったとは言えない」という理由で無罪判決が下されましたが、高等裁判所では逆転して父親に10年の実刑判決が下され、最高裁は2020年11月に上告を退け、その診断を確定させました。(名古屋地岡崎支判平成31年3月26日、名古屋高裁判令和2年3月12日)。
また、酩酊状態の女性に対する性犯罪についても、「女性が目を開けたり、何度か声を出したりしたことなどから、女性が許容していると被告が誤信してしまうような状況にあった」として無罪となる事例が複数存在します。
一審で無罪判決が下されたりと、部分的に加害者を擁護するような判決が出てしまい、多くの人が誤認してしまうことも、加害者更生を難しくさせる一つの要因と言えるでしょう。
ハラスメント加害者の更生方法
ハラスメントの加害者が更生するためには、単に「反省する」だけではなく、根本的な意識改革と行動の変容が必要です。加害者が自身の問題を認識し、社会的な影響を理解した上で具体的な対策を講じることが求められます。
ハラスメント問題は、加害者だけでなく、被害者や職場全体に影響を与えるため、更生の過程には多角的なアプローチが必要です。ここでは、加害者が更生するための4つのステップを解説し、どのように社会復帰を目指すべきかを考えていきます。
➀社会的に認知的不正義が起きている事態を理解する
ハラスメント加害者の更生において最も重要なのは、自分の行為がどのような社会的背景のもとで生じたのかを理解することです。特に、ハラスメントの問題が長年見過ごされてきた背景には、「認知的不正義」と呼ばれる状況が関係しています。
認知的不正義とは、ハラスメントとは何かについて社会的に共通言語のないことを指します。共通言語がないため、加害者の更生のための対話ができないということが問題視されています。更生を目指す加害者は、自らの行為を「個人の問題」ではなく、「社会の歪みの中で生じたもの」として捉え直し、根本的な価値観の見直しを行う必要があります。
➁加害者・被害者・第三者の誰もが「負の結果」となっていることを理解する
ハラスメントが発生すると、被害者だけでなく、加害者や周囲の第三者にとっても「負の結果」となります。被害者が精神的・肉体的な苦痛を受けることは明白ですが、加害者自身も社会的信用を失い、職場での立場を失うことがあります。また、ハラスメントが発生した職場では、周囲の同僚や上司も不安やストレスを感じ、職場全体の雰囲気が悪化してしまいます。さらに、企業のブランドイメージが損なわれ、訴訟問題に発展することもあります。
このように、ハラスメントの影響は一人の問題にとどまらず、組織全体に悪影響を与えるのです。加害者が更生するためには、「自分の行為がどのような負の連鎖を引き起こしたのか」を冷静に振り返り、自身の行動の結果を直視することが不可欠です。
③治療的コミュニティへ参加する
ハラスメント加害者の更生には、専門的な支援を受けることが非常に有効です。特に「治療的コミュニティ」と呼ばれるプログラムへの参加は、加害者が自身の行動を見直し、より良い人間関係を築くための重要なステップとなります。
治療的コミュニティでは、加害者が自身の価値観や行動のパターンを振り返り、再発防止のための具体的な方法を学びます。また、同じような経験を持つ人々との対話を通じて、自分の行動が他者に与えた影響をより深く理解する機会が得られます。日本では、DV加害者や性犯罪者のためのプログラムが導入されており、ハラスメント加害者の更生にも応用できる取り組みが進められています。加害者が本気で変わろうとするのであれば、こうした専門的なサポートを積極的に活用することが重要です。
➃自分自身の「譲れない価値観」に正しく向き合う
更生の過程では、自分が「譲れない価値観」と正しく向き合うことも重要なポイントになります。多くの加害者は、「自分の考えは正しい」「相手が過剰に反応している」と思い込んでいるケースが少なくありません。しかし、ハラスメントの本質は、「自分がどう思うか」ではなく、「相手がどう感じたか」にあります。
そのため、加害者は自分の価値観を一度疑い、「本当にそれが正しいのか?」を見つめ直すことが求められます。たとえば、「厳しく指導するのが当たり前だ」という価値観を持っている場合、その指導方法が本当に相手の成長につながるのか、別の方法はないのかを考える必要があります。こうした自己分析を通じて、より適切な行動を選択できるようになれば、再発防止にもつながります。
自分自身の「譲れない価値観」を知ること=職場関係改善の第一歩
自分自身の価値観の中には、自分で認知していないこともあります。その認知していない価値観を「譲れない価値観」といい、譲れない価値観を知ることが、職場関係改善における第一歩です。
当サイトの「ドボン診断」を利用することで、自分自身の育ってきた環境や、環境から生まれる譲れない価値観を家族心理学の知見から可視化することができます。まずは自分自身で認識するところから始め、無意識のうちにハラスメント加害者にならない対策を講じましょう。