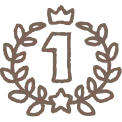婚活の難しさの一つに、個人の成長する過程での経験、環境、ライフスタイルが多様化しているということがある。価値観の一致をパートナー選びの条件に掲げる人が多いが、こうした状況では一致する相手を探すこと自体が困難であり、結果としてよい相手に巡り合えないという話は多い。こうした問題を解決するために開発されたツールがドボン診断だ。今回、ドボン診断の開発者である1tonariの村井真子が、学術的エビデンスに基づいた設計で監修協力を仰いだ黒澤泰氏とともにパートナーの関係性について対談した。

黒澤泰/茨城キリスト教大学心理福祉学科 准教授
博士(教育学)、臨床心理士・公認心理師。臨床心理学、臨床社会心理学を研究領域とし、夫婦間でのストレスコーピングなど二人以上の人がいる状況としての対人関係、及び、個人と環境との相互作用について研究を進めている。書籍に「仕事と家庭の相互影響下における夫婦二者間コーピング」、論文に「Dyadic Perspectives on Predictors of Marital Satisfaction in Heterosexual Japanese Couples」等。ドボン診断の開発監修として関与。
目次
夫婦のペアデータを扱う夫婦二者間コーピング研究
村井真子(以下、村井):私がドボン診断という、育ってきた環境から自分の価値観を明確化し、パートナーシップのあり方を考える診断の構想を持ったとき、いろいろな先生の論文や著書を読みました。そのとき黒澤先生のご研究を知って。ワーキングカップルの研究がとても少ないなかで、先生のご著書に出会ったときは大げさでなく「これだ!」と思いました。
黒澤泰(以下、黒澤):私がやっている研究は、家族心理学という領域に入ります。この領域はジェンダーを専門にされている先生が多く、また、女性の研究者も多いです。結果的に、女性の権利向上や、親子の関係、もっと言えば母子の関係の研究が圧倒的に多いです。現状は、男性でこの分野を専門に研究している学者は少ないです。だからこそ男性である自分がこの領域に取り組む意義は感じており、テーマとしてもデータとしても珍しい夫婦やカップルを対象として研究しています。
村井:なぜ夫婦の研究は少ないのでしょうか。当事者になる方はたくさんいらっしゃると思うのですが。
黒澤:夫婦研究はカップルカウンセラーなど臨床をされている臨床家の方が取り組む例が多いのですが、データを取ってエビデンスを積み上げて、という研究手法よりも、目の前で悩んでいる方をどう支援するか、というところに重きを置かれています。私の場合は、ペアデータ、つまり、夫婦それぞれからデータを取る手法や、ジョイントインタビューと言って夫婦1組に対して同時にインタビューを行う手法をしているところに特徴があると思っています。
村井:一方からだけの視点では、かなり主観が入った調査になってしまいそうですから、夫婦それぞれからデータを取るということは重要だと思います。特に今、これだけ価値観が多様化していますので、相手に対してまっさらな気持ちで評価する、相手との関係性を主観抜きで判断する、というのは難しいことではないでしょうか。
黒澤:同感です。私の場合、学部生の時に最初に取ったデータは父親のデータだったんですよ。そのあと、ワーキングマザー、ワーキングファザーのデータを取った。そうすると段々ペアデータが集まってくるんですね。最近は、男性も積極的に取り組んでくれるのですが、そうするとなぜか女性もやってくれる。男性が研究参加に積極的だと女性も協力してくださる傾向があります。

うまくいく夫婦とうまくいかない夫婦の違い
村井:学術的に長く関係が続く、幸福な関係性というカップルの条件はあるのでしょうか?
黒澤:その質問には、長く続かないカップルの関係性を知る必要があると思っています。「愛する二人別れる二人―結婚生活を成功させる七つの原則」(ジョン.M.ゴットマン , ナン・シルバー,2000,第三文明社)という本を書いたジョン・ゴットマン博士(ワシントン大学名誉教授・ゴットマン研究所所長)は、興味深い実験を経て破綻する夫婦の特徴としていくつかのサインがあることを指摘しています。そのうち、3つのサインを紹介いたしますね。
1つ目のサインは出だしの悪い会話です。相手に対する皮肉や非難から始まる会話では関係性はうまくいかないとされます。例えば「昨日の帰り遅かったけど、どうせ夜遊びしていたんでしょ」のような発言から会話をスタートするのはダメだということですね。
2つ目のサインは非難です。二人の間にある問題を事象として見ずに、相手の人格に起因するものだとして相手の人格を否定したり、中傷するような話し方はやはりうまくいかないとされます。頼んでいた車のガソリンが入れられていない事実があったときに、「入れてくれって何回も言ったのに何で忘れるの?無責任じゃない?あなたっていつもだらしないんだから!」みたいなパターンです。
3つ目のサインは悪い思い出、つまり過去の二人の歴史を不快な方に悪い方に書き換えていく、というものです。幸せな夫婦は二人にとってよかったことを記憶していて何度も思い起こしますが、不幸な夫婦は過去の出来事に対して「今思えばあの時は寒くてつまらなかった。思い出のように考えていてバカみたい」と今の感情を起点にその時の思い出を悪い思い出に書き換えてしまう傾向があるとされます。
なので、これらを逆にすれば、幸せなカップルの関係のあり方が分かるのではないでしょうか。
村井:つまり、相手に敬意をもって話しかけ、問題は自分にも責任の一端があるという態度で相手の人格を否定せずに話し、よい思い出を記憶し、楽しかったこと、幸福な体験をたくさん共有する、ということですね。
黒澤:私はこの不幸な関係性において、「いいわけ」や「逃避」という行動があることに注目しています。問題が自分の側、あるいは二人の双方にあるのではなく、相手側に責任があるという態度や、そもそも話し合えない、口をつぐんでしまう、出て行ってしまうというような対話をさける態度は、関係性にとってプラスの影響がないと考えています。
村井:その通りです。私の業務領域であるハラスメントの問題も、「いいわけ」や「逃避」によって悪化することは多いです。相手に原因を押し付けたり、対話すること自体ができない。

個人と関係性のトレード・オフ
黒澤:他責性、というのは関係性にとっては毒なんだろうと思います。私にとって大きなテーマでもあるのですが、個人にとって負担がかかることでも、関係性にとってはよい効果がある、ということがあるんですよ。例えばストレスがかかる出来事があって、それを相手にぶつけることは個人にとってはストレス発散になりますが、ぶつけられた相手との関係性にとっては害になる。実際、がん患者とその配偶者の研究では、配偶者の病気というストレスフルな状態に対して我慢する、耐えるということは配偶者自身のストレスではあるのだけれども、患者である相手にとってはよい、つまり、夫婦という二人の関係性ではポジティブに働く、という話もあります。
村井:とはいえ、自分にとってストレスが強くなりすぎると、それはそれで害になりますよね。こと結婚ということでいうと、夫婦といえどそれぞれ価値観や人格が違うわけで、衝突はむしろ関係の前提になると考えられます。その時に、自分が耐えられないことと、耐えられることがあるのではないかと思うのですが。
黒澤:先ほど紹介した本の中で、ゴットマン博士は、心理学者のダン・ワイルの「配偶者を選んだ時、それは、とりも直さず、その後の十年、いや五十年間、二人の間で解決できない問題と対決することでもある」という言葉を紹介しています。話し合ってもなんともならないことが多いのではないでしょうか。
村井:結婚へ至る道筋も非常に複雑になっています。かつては自分の家の価値観をよく知っている仲人が、「ここなら釣り合うだろう」と家柄、いわば家のひととなりを知ったうえで意見が相違しなそうな組み合わせを作っていた。もちろんうまくいかない組み合わせもあっただろうけれども、離婚は世間体や経済力の問題でできないから耐えた、という話もよく聞きます。
黒澤:私の研究でも、夫婦間の葛藤が発生した後に話し合えるかどうか、という視点があり、葛藤後に話し合えると結婚満足度が高いんです。この現象は10年前のデータと、最近取ったデータで知見が一致しているので確度の高い話です。
村井:ドボン診断のデモ版を結婚間近なカップルにやっていただいたことがあります。お二人の合意の元、二人それぞれの結果を開示しました。そのとき、当然ながらお二人の結果は同じではなくて、こだわりの多い女性と、こだわりの少ない男性の組み合わせだということが分かりました。その時に男性のほうが、「君はこだわりがたくさんあるんだね、僕はほとんどないから合わせるよ」と言われて。女性も「いや私に合わせてばかりだと疲れるから、あなたの大事にしたいことはちゃんと言って」と。こういう、お互いを受容するやりとりをされている姿は本当に尊いなと思いました。お互いを尊重しつつ、対話の道を開いている。
黒澤:夫婦には永続する問題と解決できる問題があって、それは分けて考えたほうがいいと考えます。永続する問題とは、夫婦それぞれの実家の経済力や容姿、障がいや病気の有無のように、本人の努力でどうにかならないものですね。解決できる問題は、休みの予定や出かける先の変更などです。問題ではあるけれども話しあう余地があるものといっても良いかもしれません。先ほどの村井さんの例では、女性には永続する問題に属することが男性には解決できる問題であった、と言うことなのだろうと思います。ドボン診断は、永続できる問題を可視化してくれるツールなんです。

ゆずれない価値観を明確化することで相手を尊重する
村井:ドボン診断では、自分が育ってきた環境、特に両親からどのように育てられてきたかについて今の自分が評価する構造を取っています。それによって、とても評価できるところ、全く評価しないところ、グラデーションがあるところが明確になる。明確になることで、自分が歩み寄れないところ、相手が変わりようのないところ、というのもはっきりします。
黒澤:相手にとって永続する問題であれば、放置する、触らないでおいておくということも大事なのではないかと考えています。
村井:私たちには、お子さんが授かった後も夫の態度が変わらない、という妻側の不満がよく寄せられます。長年の趣味をやめてくれない、とか、ライフスタイルを変えてくれないというものですね。でも、それは当たり前のことで、人はそう簡単に変わらない。それはその人の人格形成の過程によって生じているから、変えようがない、ということもあります。
黒澤:自分の人生で大事にしているものが多すぎても難しいですが、トップ3くらいは尊重を前提にした方がいいと思いますね。それが自分にとって価値を感じられないことであっても、相手にとって譲れないものは尊重する。それを奪うことは相手の人格を否定することになってしまうからです。自分が大事にしているものがあるのと同時に、相手には相手の大事にしているものへの歩み寄りの姿勢は大切ですね。相手を支配しようとしてはいけないと私は考えます。
村井:二人が幸せになるための結婚というプロセスが、相手を支配するものであってはならない、ということですね。その誤解をしないように自戒しなければならないですね。
ドボン診断開発秘話と使い方
村井:開発に当たり、私たちがこだわったことは、こと結婚を視野に入れた診断というものがたくさんあるなかで、エビデンスベースであること、受検された方がきちんと使えるものであること、ということでした。
黒澤:ドボン診断を作る際、予備調査をし、それをもとに本調査を作りました。信念ではなく、データに基づき、エビデンスを意識しながら診断作成を試みました。これは私たちがこだわったことですね。なので言い回しや表現はちょっと難しいですが、それを安易に変えてしまうとエビデンス自体が弱くなってしまいます。今後バージョンアップする際に、改めて予備調査をして、それに基づいて設問を変える、ということは検討してもいいと思いますよ。
村井:ドボン診断で孤独は減らせると思っているんです。自分が大事にしているものと歩み寄れるものが切り分けられることで、カップルである二人の関係性をよくする手だてが分かる。例えば、自分がどんなに遅くなっても料理を作る、ということを頑張ってやっていたとして、相手にとってはそんなに響いていないということがあります。そのときに、「相手にこんなに頑張っている自分の努力を認めてよ!」というアプローチより、「そうか、週1回はお惣菜を買ってもこの人が問題視しないなら、忙しい時はそうしよう」というほうが関係性にとってはヘルシーですよね。
黒澤:我慢できないものをはっきりさせる診断であると同時に、我慢できるものもはっきりさせる診断なんです。海外では我慢や譲歩は悪いものとして取られがちなんですが、結婚という流動性の低い関係においては我慢できることはある程度我慢する、ということが関係性の継続という観点では求められるのではないでしょうか。
村井:それはなにも法律婚というか、男女のカップルだけの話ではないですよね。事実婚もそうですし、同性愛のカップルでも起こりえる。
黒澤:このプロジェクトは二者間の関係構築を扱っているのですが、二者間の関係をよくする、ということを考えれば同性パートナーだけではなく、親子やビジネスパートナーなどの関係構築にも活用しうるものだと考えています。
村井:今回の設問では好意的セクシシズムなどに根差している設問もありますが、それがいい悪いという判断はしない。イデオロギーとしての価値観と、現実に自分が持っている価値観はイコールではないから切り分けて考えたほうがいいということですね。
黒澤:何事もバランスというものがあって、カップルの場合、先ほど話した個人としての幸福と、関係性においての幸福というものが一方に偏っている状況では、関係としてはヘルシーではないと思います。でも、このバランスは関係性の当事者たちが決めていいとも考えます。
村井:関係性のサステナビリティという観点では、関係を維持することへのモチベーションをいかにもつか、持てるかということにあるように思います。これはどこに根差しているものなのでしょうか?
黒澤:家族は経済的利害関係がない関係性なんです。経済的な関係になるとどうしても利害が生じます。でも家族は一緒にいることにコストがかからないし、免責事項も読まなくていいし、進捗も確認されない。そこにただいることを許される関係なんだと思うんです。
村井:そこにただいることを許される、ということが、二人の関係を作る上での基本になる部分なのかもしれないですね。
(2024.11.23 オンラインにて対談)

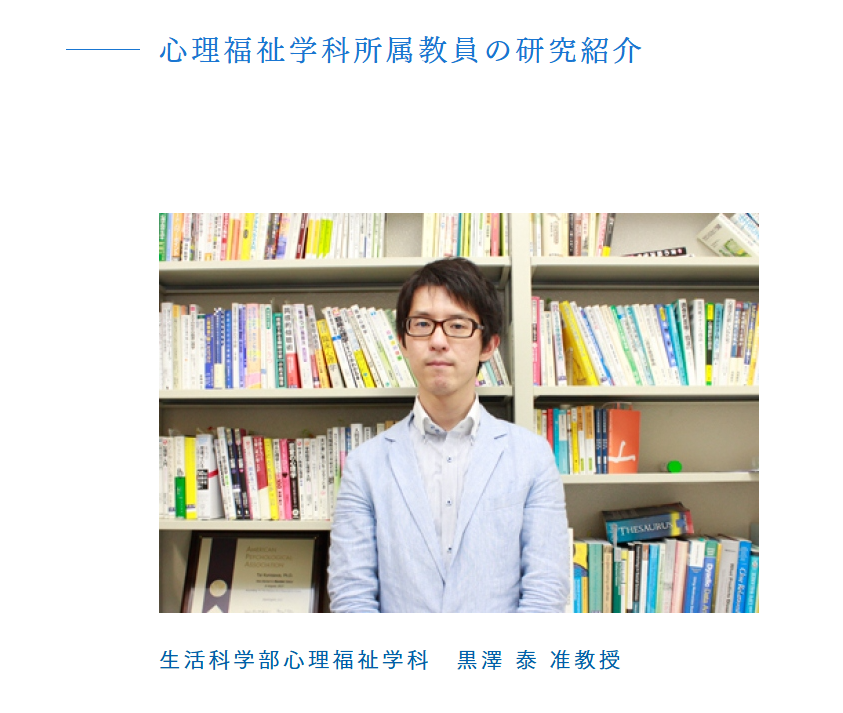
心理福祉学科:研究紹介 黒澤 泰 准教授 | 茨城キリスト教大学
本対談について、黒澤 泰 准教授の研究業績として紹介されています。